【エリア】:風吟の谷
【必殺技】:[虹鱗闖入]
【種族】:龍族

いつかにこの奇妙な大陸に落ちたのか忘れた。しかし、この自由で面白い異世界にすぐに慣れてしまった。
巨大な龍は時々空で旋回して飛んでいで、猫耳付きの獣人の尾は君の腰を回って、森林の草花は催情の香りを発散している~
獣人領地の芝生の上で、神秘的な水域の波の間で、いつも興奮しているホルモンの沖突が激情で発生している。
ある平日なりの朝に、賢い鹿人から借りたNothosaurガイドをめくって、
「虹欲白龍という龍は、性が高くて、人の形に幻化することができて、自発的に催情のにおいを発散することができる…」

急所まで目を通していると、突然、本棚の後ろに一筋の光を気にする。本をどけて
「えー、これは先日赤兎をお見舞いにいった帰りに拾った化石じゃないか…」
この時、今日深林の中ですばらしい異花の展覧会があることを突然思い出して、見逃したくて急いで出かけて、手当たり次第に化石を机の上に置きてしまった。
夜、暖かいたき火のそばで、ガイドを研究し続けて、産卵できる食人花を馴化する方法を見つけるよう考えている....
何か肘に触れて、ごろごろとテーブルから落ちた。
「いや....」
やはりそれをキャッチしないで、化石はそんなに偶然にはたき火の盆の中に落ちて、君は急いで手を伸ばして助けに行っても、指は熱い炎に触れた一瞬に、やけどをして手を引っ込めてしまった。
「まあ、ただ石だね....かがり火が消されないように」
眠気に襲われ、君はかがり火鉢に樺の木を落として寝た。そのとき、化石は小さな口をあけ、虹のような光を放った。
夢の中に、ダイヤモンドのような白い光を見た。

また、知らない非人族の男がその中にいて、まつげの一本一本は、春を誘うように気持ちが流れていて、彼は白衣つきの貴族として、襟を半分あけて、人をひっかく鎖骨と胸元の真っ白な肌をのぞかせて、にやにやしている。背後の白い巨大な翼と頭上の龍の角は、彼が龍族の一員であることを示している。彼の体つきは刀と斧をはずられるように、はっきりしている。それと同時に、火の光に照らされたところで、腰股の上には腹筋が整然と並んでいる。上を見ると、胸筋が張りめぐらされ、背中の白い翼は神聖な輝きを放っているようになった。

「君は……私は……」
伝え方を組み立てていて、何を言えばいいかわからない、それは夢だか?なぜ空気の中で少し火照っている感じがあるか、奇妙な要素が体の中で燃えてきた。
「私は炎の息子であり、谷の主であり、また竜の息の代弁者である」
彼は途方にくれた君の眉と頬骨を親指で細かく触っている。
「君の召使いでもあります。ご主人様」
虹欲白龍は君の耳に身を寄せ、貴族気味な声でささやいた。
君はその幻のような前置きの中に、この白い紳士の声と驚嘆すべき美顔とに、夢中になってしまった。知らず知らずのうちに、男根が高くて硬くなり「夢なら気を狂わせてやろう」と思って、「主人の世話をどうすればいいか知っているか?」君の声は鼓動と共鳴しているようになった。
その白金色の美青年はひざまずいた様子を見て、両手が君の腹筋に探って、彼の鼻はすでに「そこ」を辿っていた。君の巨根が彼のあたたかい手の中で搔き回され、掌から伝わった摩擦が淫文の火を焚かせた。彼は形のいい唇を開いて、かすかに君の硬い男根を含んだ。熱くて引き締まった口の中に入ると、君も満足そうに息を吐いた。彼は見事に褒められたかのように、さらにこの巨大な性器を舐めている。この火がすでに体全体を燃やしていることを気付き、ただ短い喘ぎと抑えきれないうめき声で、人にこの尋常でない香りを体得させることができる。

その時、彼の動きが止まってしまった。見下ろすと、白金色の聖光を放つ神器が、見事に目の前に現れた。神器の上には、大理石の浮彫りのような竜族の印が繁雑に浮き上がっている。丸みを帯びた突出した頭部は、天を突き抜けるように天国の神秘を覗き込んでいるように、聖潔さの中には計り知れない力がある。
残された理性で、淫欲に完全に溺れないようと自分を説得していたが、彼が立ち上がって君を転がし花穴を撫でる時、最後の理性の線が切れてしまった。
「うーん……」
淫らな声を上げまいように唇を嚙んだ君は、
「おかしい、俺が主人じゃないか…」
しかし、抑えきれない欲望が残された理性を焼き尽くした。
「それもいいけど……」
彼の熱い亀頭は尋常でない熱さを伝えて、ただでさえ高い情欲を炙っている。
彼は君を抱きしめて、律動を始めた。それは拒否を許さない、独占欲に満ちた操作だ。彼の奇妙な気配に、君は体が萎え、体の底でもほとんど抵抗を諦めていた。深く突き刺すたびに、摩擦で赤く腫れた秘部が思いきり切り裂かれた。何度も引き抜くたびに、絞り込まれた穴の筋肉が、またしても太い肉稜でこすられた。龍族が与えた沖撃で、ゴツゴツと突き上げられた龍根は、次々と抜き差しを缲り返しながらセックスを盛り上げ、ついに、下腹部にゴツゴツとした竜根の行働を露わにした。ひとしきり夜風が吹いて、かがり火が暗黒に燃えて消える時、ダッシュを終えた白龍は肉柱全体を思いきり裏庭の中に突き立てて、君の線のはっきりした小腹の上ではっきりと1本の太い突起を持ち上げられて、絶えず拍働している。その拍動とともに線が消え、下腹部がふくらんでいき、虹欲白龍の満ちた精液が溢れて一面に滴り落ちたところで、彼はとうとう射精を止めた。

大きい汗をかいて目を覚ますと、この完璧な貴族を見て、しだいに痴態が現れた。彼はあたたかく乾燥した大きな手が、少し乱れた赤毛を撫でたまでに、君は目の前にいる神は幻ではなく、実在する存在を気づいた。こんなに強くて完璧で、神聖で優雅な存在である。
「おはようございます…ご主人様」



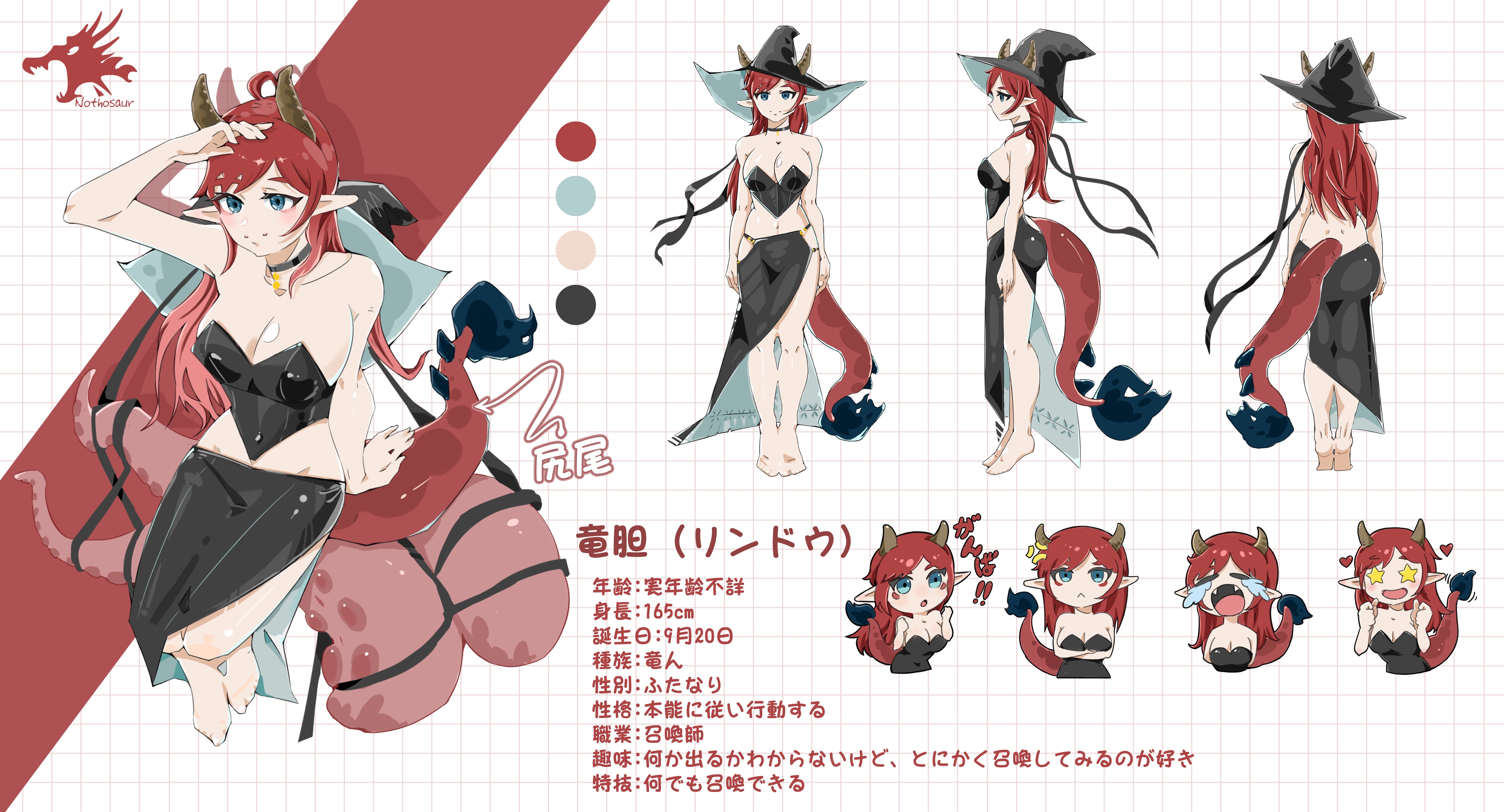
Leave a comment
All comments are moderated before being published.
This site is protected by hCaptcha and the hCaptcha Privacy Policy and Terms of Service apply.